
SAP ERP 6.0は、2027年に標準サポートが終了する予定です。
終了後も利用を続けることはできますが、脆弱性への修正パッチが提供されなくなるため、サイバー攻撃や不正アクセスのリスクが一気に高まります。
S/4HANAへ移行するにしても、連携停止やデータ不整合などにより業務が止まるリスクもあるため、慎重な対応が求められます。
本記事では、サポート切れのSAP ERPを使い続けるデメリットと、リスクを抑えながら移行を進める方法を解説します。
目次
SAP ERP 6.0の標準サポート(メインストリームサポート)は、2027年12月末で終了します。
当初は2025年12月末が期限とされていたため「2025年問題」と呼ばれていましたが、SAP社がサポート期間を2年延長したことにより、「2027年問題」として改めて注目を集めています。
サポート期限が終了すれば、セキュリティパッチや新機能が提供されなくなるうえに互換性が維持できなくなり、システム全体の連携が不安定になる恐れもあるでしょう。
長年にわたり多くの企業の基幹業務を支えてきただけに、「現行システムをいつまで使うか」「どのように移行を進めるか」という判断が迫られています。
SAP ERP 6.0のサポート終了日はEhP(エンハンスメントパッケージ)のバージョンによって異なるため、自社の環境が「いつまで安全に使えるのか」を正確に把握しておくことが重要です。
以下に、通常サポートの終了時期と延長サポートの終了時期をまとめました。
| バージョン | 標準サポートの終了時期 | 延長サポート終了時期 |
|---|---|---|
| SAP ERP 6.0(EhP1〜5) | 2025年12月31日 | なし |
| SAP ERP 6.0(EhP6〜8) | 2027年12月31日 | 2030年12月31日 |
SAP ERPは、サポート期限を過ぎても運用を継続すること自体は可能です。
しかし、保守が終了した環境を維持することは、セキュリティ対策の遅れや障害対応の負担増など大きなリスクを伴います。ここでは、サポート期間が終了したSAP ERPを使い続けることによるデメリットについて解説します。
SAP ERPのサポートが終了すると、脆弱性を修正するためのパッチが提供されなくなります。一見、利用するうえでは問題がないように見えても、既知の脆弱性を狙った侵入や不正アクセスの危険性が一気に高まる状況です。
また、監査や内部統制の観点からも「保守切れシステムの継続利用」は指摘を受けやすく、情報漏えいだけでなく経営上のリスクにもつながりかねません。
保守期限が切れると、OSやデータベースの更新検証が行われなくなり、環境をアップデートした際に不具合が生じるリスクが高まります。
特にSAP ERPは会計や人事・販売などを統合的に管理する基幹システムであるため、互換性が損なわれるとデータ連携が途切れ、業務全体に影響が及ぶ恐れがあります。
安定した運用を維持するには、サポート期限を正確に把握し、十分な余裕をもって移行計画を策定することが重要です。
新機能や最適化アップデートの提供が止まるため、業務の効率が低下する可能性があります。
自動化を図ろうとしても、クラウドサービスやSaaSを十分に活用できず、既存機能の制約に縛られたままになるでしょう。
その結果、業務部門からの要望をすぐに反映できず、現場の生産性やユーザー体験が徐々に低下していきます。
さらに、法制度やグローバル展開などビジネス環境の変化にも柔軟に対応できず、競合他社に遅れを取ってしまいます。
サポートが終了した製品では、障害が発生してもベンダーから十分な技術支援を受けることができません。
外部ベンダーに調査や修正を依頼する方法もありますが、高額な費用が発生しやすく、原因の特定や復旧にも時間がかかります。結果として、システム全体の停止につながるリスクが高まります。
現在の保守基準料金に2%を上乗せすることで、保守期限を2030年末まで延長することが可能です(延長保守サービス)。
ただし、延長保守はあくまで時間を買うための措置であり、通常より高額な費用が発生します。さらに、その間に周辺システムの更新が進むことで、互換性を保つための個別改修や運用負荷が増えてしまうかもしれません。
移行を先送りすればするほど技術者の確保も難しくなり、ノウハウの断絶や移行難度の上昇といった新たなリスクを招く可能性もあります。
2027年問題への対応策として、SAP S/4HANAへの移行を検討しているご担当者も多いでしょう。
ただし、十分な準備を行わずに移行を進めると、思わぬトラブルを招く恐れがあります。
ここでは、移行をスムーズに進めるために押さえておきたいポイントをご紹介します。
SAP社は「SAP ERP 6.0」の後継として「SAP S/4HANA」を推奨しています。
同じベンダー製品であるためこれまでの運用ノウハウを活かしやすく、オンプレ型・クラウド型・ハイブリッド型の中から選べる点も魅力です。
ただし、「同じSAPだからスムーズに移行できる」と安易に考えてしまうのは危険です。「SAP S/4HANA」は設計思想や標準機能が「SAP ERP」から大きく変更されており、単純なリプレースでは整合が取れず、想定外の工数やテスト負荷が発生するケースもあります。
まずは「期間」「刷新範囲」「コスト」の優先度を明確にし、関係者間で合意を取ったうえで、影響の大きい業務領域から段階的に進める方針を固めましょう。
移行プロジェクトが長期化する原因のひとつが、データ品質です。
部署ごとに独自のルールでデータを登録していると、重複や表記ゆれ、欠損といった不整合が生じやすくなります。
特にSAP S/4HANAは広範な業務領域をカバーするため、品質の低いデータをそのまま移行すると手戻りが多発するリスクがあります。
事前に「件数一致」や「合計一致」などの合否基準を定め、早い段階でデータ整備を進めておくことで、移行期間を大きく短縮できるでしょう。
SAP S/4HANAは処理スピードが速く、モジュール間や外部システムとの連携にも優れています。
しかし、十分な計画を立てずにカットオーバーを迎えると、連携不具合によって業務全体が停止するおそれがあります。
トラブルを防ぐには、早い段階で受け渡し方式を洗い出し、監視・通知・再実行まで含めた運用設計を整えておくことが欠かせません。
SAP ERPからS/4HANAへ移行する場合は、既存のアドオンをそのまま引き継ぐことも可能です。
ただし、両システムでは仕様が異なる部分も多く、従来環境で使用していたアドオンやカスタマイズが動作しない、あるいは想定外の影響を及ぼす可能性があります。
そのため、移行計画を立てる際には、各アドオンが本当に必要かを見直すことが欠かせません。
移行先や周辺システムの標準機能で代替できるものは削除し、自社の強みや独自ノウハウに関わる部分のみをブラッシュアップします。
開発・業務・経営が協議しながら整理を進め、移行コストの最適化と業務標準化を両立しましょう。
2027年問題への対応としてシステム移行を進めたくても、ITエンジニアやパートナー企業の確保が難しく、従来と同じスケジュールや予算での実行が困難になりつつあります。
こうした課題を解消する手段のひとつが、「ASTERIA Warp(アステリアワープ)」のS/4 HANA Cloudアダプターです。
ノーコードでデータの取得・登録・更新・削除を設定できるため、移行から本番運用までのつなぎ・再実行・通知といった連携処理を短期間で構築できます。
実際に、i-PRO株式会社様では、ASTERIA Warpを用いてS/4HANAを含むシステム連携をわずか4カ月で構築しました。テンプレート活用により開発コストを約10分の1に抑え、23のシステムの立ち上げと、214本という数のシステム連携インターフェースの構築を遅延なく完了したのです。
SAP ERP 6.0のメインストリームサポートは2027年末に終了します。その後もシステムを使い続けることは可能ですが、セキュリティリスクの増大や保守コストの上昇など、運用上の負担が大きくなります。自社システムのサポート期限を確認し、余裕をもって新システムへの移行準備を進めることが重要です。
S/4HANAを選定して2027年問題に備える場合は、次のポイントを意識しましょう。
ASTERIA Warpの「SAP S/4 HANA Cloudアダプター」を活用することで、既存のSAP ERPからS/4HANAへのスムーズな移行を実現することができます。SAP ERPへの移行を検討しているご担当者様は、ASTERIA Warpの活用を検討してみてはいかがでしょうか。

PM・SE・マーケティングなど多彩なバックグラウンドを持つ「データ連携」のプロフェッショナルが、専門領域を超えたチームワークで「データ活用」や「業務の自動化・効率化」をテーマにノウハウやWarp活用法などのお役立ち情報を発信していきます。

![MDMコラム[入門編]第1回:マスターデータ管理(MDM)とは?メリットや進め方、導入事例をご紹介!](https://www.asteria.com/jp/wp-content/uploads/2013/01/warpblog_88671186_title01.png)
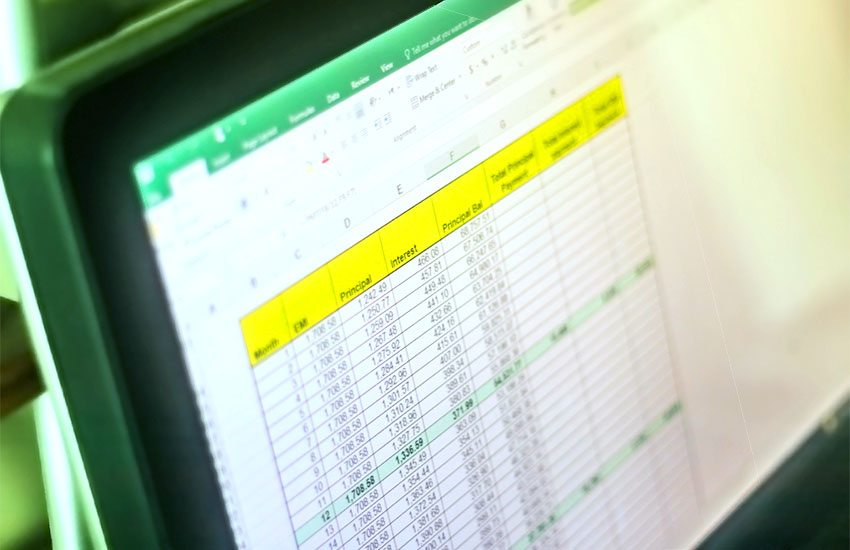


Related Posts

ASTERIA Warp製品の技術情報やTips、また情報交換の場として「ADNフォーラム」をご用意しています。

アステリア製品デベロッパー同士をつなげ、技術情報の共有やちょっとしたの疑問解決の場とすることを目的としたコミュニティです。