
企業のDX推進が進む一方で、レガシーシステムの課題を抱えながらも対応に踏み出せていない企業は少なくありません。本記事では、「企業のモダナイゼーションに関する実態調査レポート」の結果をもとにモダナイゼーション実現への障壁とその背景を整理しました。
また、レガシーシステムの運用課題への解決策としてノーコードで進める段階的モダナイゼーションや、その具体的な進め方についてもご紹介します。
目次
2025年2月、日経クロステックActive(協賛:アステリア)が「モダナイゼーションに関する実態調査」を実施しました。
回答があった502社のうちの多くが、属人化やブラックボックス化、サポート終了といったリスクを認識しながらも、未だレガシーシステムを使い続けている現状が明らかになりました。
原因としては、システム構造の複雑さ、IT人材の不足、移行コストへの不安や経営判断の停滞など様々な要因が挙げられます。
こうした現状を踏まえると、業務への影響を抑えながら、段階的にモダナイゼーションを進めていくアプローチが有効です。次の章からは、調査結果をもとに具体的な進め方を解説していきます。
「利用しているレガシーシステムの課題をお聞かせください(複数回答可)」という問いに対しては、「管理・運用の属人化」(160件)、「システムのブラックボックス化」(135件)、「サポート切れ」(87件)などの回答が上位に挙がりました。
たとえば、特定の担当者しかシステムの操作方法や構成、運用フローを理解しておらず、その人が異動や退職で不在になると、業務がストップしてしまうケースもあります。さらに、軽微な改修であっても外部ベンダーへの依頼が必要になり、対応のたびにコストと時間がかかってしまうという問題も深刻です。
また、保守が終了したシステムを使い続けることで、セキュリティリスクの高まりや障害発生時の対応遅れといったリスクも抱えています。
仕様が十分にドキュメント化されていないことで、DXの推進が停滞するなど、長期的な成長を阻む要因にもなりかねません。
こうした運用上の課題がなぜ放置されがちなのか、その背景について次の章で詳しく見ていきます。
「レガシーシステムを新システムへ移行する際に課題となること」を尋ねたところ、「人材不足」(125件)、「既存システムが属人的すぎる」(119件)、「費用対効果が見えない」(113件)といった声が特に多く挙がりました。
さらに「今までのやり方を一新するにはリスクがある」(83件)、「データ連携が困難」(64件)、「経営陣の理解が得られない」(52件)といった回答からは、技術面の制約だけでなく、社内調整の難しさや変化に対する心理的なハードルも見て取れます。
すべてを一度に刷新しようとすれば、現場が混乱し、新しい仕組みが根づかずに形だけの改革に終わってしまう恐れもあります。複数の要因が絡み合った状態で、慎重にならざるを得ないのが企業側の本音かもしれません。
とはいえ、レガシーシステムを使い続けることにも、業務効率の低下やセキュリティリスクの増大といった問題が伴います。そのため、「リスクを抑え、小さく始める」アプローチが現実的で実行可能な道筋だといえるでしょう。次章では、その進め方について詳しく解説していきます。
このような「モダナイゼーションの障壁」を企業はどのように乗り越えるべきなのでしょうか。ここでは、調査結果で明らかになった主な課題に対する対応策を解説します。
IT人材の不足が深刻化する中、企業においてはモダナイゼーションの担い手も不足しています。このような中で求められるのが、非IT人材でも利用できる「ノーコードツール」の活用です。
ノーコードツールでは、プログラミングを行うことなく、画面上で必要なシステムを開発できます。現場に近い担当者がシステム連携や構築に自ら関与できる環境を整えることで、IT部門への過度な負荷を分散し、モダナイゼーションの取り組みを前に進めやすくなります。
長年運用されてきたシステムは、特定のベテラン従業員しか詳細を把握しておらず、ブラックボックス化しているケースが多くみられます。このような状況はモダナイゼーションの足かせとなりやすいですが、一方でベテラン社員が退職してしまえば、誰もシステムを理解していないという危険な状況に陥ります。システム刷新の最大のチャンスは、こうしたベテラン社員が現役で在籍している「今」です。
ベテラン社員が持つ暗黙知や独自の業務ロジックを洗い出し、最新のシステム仕様としてドキュメント化・標準化することで、貴重なノウハウを次世代のデジタル資産として確実に継承することが可能です。
大規模なモダナイゼーションは、多額の投資とリスクを伴います。まずは効果が明確で、調整が容易な特定の業務から「スモールスタート」で着手し、段階的に拡大していく手法が現実的です。
小さなモダナイゼーションプロジェクトを通して得られた「削減できる作業時間」や「削減できた運用コスト」といった効果を、具体的な数値で可視化し、経営層に報告することが重要です。成功の結果を共有することが、全社的な刷新に向けた推進力となります。
レガシーシステムからの移行を一度に進めようとすると、業務への影響が大きくなり、かえって混乱や定着の遅れを招く可能性があります。
そのため、まずはデータ連携から着手し、次に基幹システムのリプレイス、そして全社最適化へと段階的に取り組むアプローチが、無理のない進め方として注目されています。
ここでは、モダナイゼーションをスムーズに進めるためのステップを、順を追ってご紹介します。
レガシー環境では、システム同士が密結合されていたり独自仕様で構築されていたりするため、新しいシステムとの連携が難しく、部門をまたいだデータ活用が困難です。そこで、まずは基幹システムには手を付けず、周辺システムとのデータ連携部分からモダナイズを始めます。
具体的には、APIの活用やETL基盤の整備、リアルタイム連携の導入といった手法により、システム間の情報の流れをスムーズにします。
部門ごとのPoC(概念実証)や小規模な連携改善からスタートすることで、既存の運用に負荷をかけずに変化を進めることが可能です。
点在していた社内データをつなぎ、可視化・利活用の基盤を整えることは、後続フェーズである基幹システム刷新や全社最適化の土台作りにもつながります。
従来の基幹システムは、すべての機能がひとつにまとまった「モノリシック構造」で構築されているケースが多く、機能の一部を変更するだけでもシステム全体に影響が及んでしまうなど、拡張性や柔軟性に乏しいという課題がありました。
そこで重要になるのが、機能をモジュールごとに切り分け、必要な部分から順に入れ替えていくという発想です。マイクロサービス化やSaaSの活用を段階的に取り入れることで、将来の業務変化にも対応しやすいシステム構成に進化させることができます。
具体的には、ERP、SCM、会計といった基幹システムをフェーズに分けて計画的にリプレイスします。その際、ステップ1で整備したデータ連携基盤を活かし、事前にマスタデータの整合性を確保しておくことが重要です。これにより、各システム間での齟齬や情報のズレを防ぐことができます。
なお、すべてを一気に移行しようとすると、現行業務との整合が取れず混乱が生じるリスクがあります。旧システムと新システムの並行運用期間を設けるなど、段階的な計画を立てるようにしましょう。
データ連携の整備と基幹システムのリプレイスが完了したあとは、各部門単位の最適化から一歩進み、企業全体としての最適化を目指すフェーズに入ります。
この段階では、BIやAIの活用によるデータドリブン経営の推進、全社共通の業務プロセス整備、そしてセキュリティやデータ品質を維持・強化するガバナンス体制の構築がポイントです。
情報の一元管理とプロセスの統一により、全社レベルでの迅速かつ的確な意思決定が可能になります。
また、ここで重要なのが「継続的な改善」に組み込む姿勢です。仕組みを整えたら終わりではなく、日々の業務や環境の変化に応じて定期的な見直しや調整を行うことが、全社最適を維持するうえで欠かせません。
段階的に積み上げてきた基盤の上に、組織横断での情報活用やプロセス統一を進めることで、迅速かつ的確な意思決定ができる経営基盤を整えていきましょう。
段階的にモダナイゼーションを進めるうえで、現場で扱いやすく、すぐに着手できるツールの存在は不可欠です。そこで注目したいのが、プログラミングの専門知識を必要とせずに開発や設定が行える「ノーコードツール」です。
IT人材が限られる現場でも導入・運用がしやすく、構築スピードが速いため、現場への定着もスムーズに進められます。処理の流れも視覚的に把握しやすいため、後からの修正や拡張も容易です。
中でも注目したいのが、10,000社以上の圧倒的な導入実績を誇る「ASTERIA Warp(アステリア ワープ)」です。ExcelやGoogleスプレッドシートなど100種類以上のアダプターを搭載しており、幅広い業務システムと素早く連携できます。
操作も直感的で、ドラッグ&ドロップで処理フローを組み立てる形式のため、システム部門以外でも扱いやすいのが特長です。さらにスケジューラ機能により、設定した処理を自動実行させることも可能です。
料金プランも5種類用意されており、月額3万円から(初期費用なし)とコスト面においても導入しやすいという特長があります。
さらに2025年8月からは、iPaaS版である「ASTERIA Warp Cloud」も加わる予定で、企業・組織規模に合ったより最適な製品・料金プランをお選びいただけます。
ASTERIA Warpはその機能、使いやすさを評価いただき、国内最大級のIT製品/SaaSレビューサイト「ITreview」のデータ連携ツール部門で「5年連続Leader」を受賞。ユーザー評価に基づき13,000を超えるSaaS・ソフトウェアを選出する「ITreview Best Software in Japan 2025」では、Top100に選出されています。

株式会社野村総合研究所(NRI)様では、老朽化した会計システムの刷新に伴いSAP S/4HANAを導入。その際、ASTERIA Warpを用いてCoupaやConcurなどの業務システムと連携する基盤を構築しました。今後のサービス追加にも対応できる、汎用性の高い連携環境を整えた好例といえるでしょう。
今回の調査からは、レガシーシステムの属人化やブラックボックス化、そしてサポート切れといった課題が多くの企業に共通する悩みであることが明らかになりました。一方で課題を認識しながらも、IT人材不足や移行コストへの不安、既存業務への影響を懸念する声から、モダナイゼーションに踏み出せていない企業が少なくないことも浮き彫りになっています。
こうした状況においては「すべてを一気に変える」のではなく、まずは影響の少ない領域から着手し、段階的にモダナイズを進めていくアプローチを推奨します。その際は、迅速かつ柔軟にデータ連携ができるノーコードツールを活用するとよいでしょう。
まずはASTERIA Warp無料トライアルを通じて、自社の既存システムとの連携がどこまで可能かを試してみてはいかがでしょうか。

PM・SE・マーケティングなど多彩なバックグラウンドを持つ「データ連携」のプロフェッショナルが、専門領域を超えたチームワークで「データ活用」や「業務の自動化・効率化」をテーマにノウハウやWarp活用法などのお役立ち情報を発信していきます。

![MDMコラム[入門編]第1回:マスターデータ管理(MDM)とは?メリットや進め方、導入事例をご紹介!](https://www.asteria.com/jp/wp-content/uploads/2013/01/warpblog_88671186_title01.png)
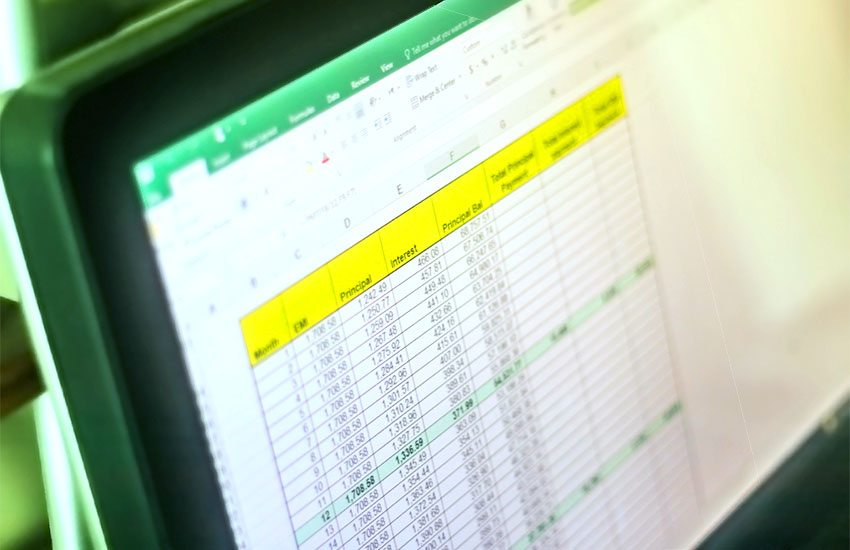


Related Posts

ASTERIA Warp製品の技術情報やTips、また情報交換の場として「ADNフォーラム」をご用意しています。

アステリア製品デベロッパー同士をつなげ、技術情報の共有やちょっとしたの疑問解決の場とすることを目的としたコミュニティです。