
3月8日、株式会社ゴルフダイジェスト・オンラインの清水様、ワタベウェディング株式会社の石毛様が発起人となり新たなスタイルのユーザー交流会が開催されました。
今回は清水様、石毛様の発案で、最初からテーブルにドリンクをご用意。アルコールが潤滑油となり普段のユーザー会では聞けない本音トークが飛び交う貴重なユーザー交流の場となりました。

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン
TECビジネスユニット システム開発担当 シニアプロジェクトマネージャー 清水 正朗 様

「いきなりディスカッションしましょうと言っても難しいと思いますので、最初に私からGDOのケースをお話しします。」と清水様より以下のような内容について実事例を交えてお話しをいただきました。
株式会社ワタベウェディング システム統括部 システム企画開発グループ 係長 石毛 信次 様

続いて株式会社ワタベウェディングの石毛様より自由に開発させたことで起きた失敗事例などをご紹介いただきました。またいくつかの課題提起をいただき、その後参加者全員でディスカッションをしました。
Q. 外注と内製の線引きをどのようにしてますか?(石毛様)
Q. 内製の場合、開発者は社員?業務委託?(石毛様)
Q. ドキュメントはどこまで整備してますか?(参加者)
Q. 社内開発ルールはどのように整備してますか?(石毛様)
などが話し合われました。
参加者からは次のようなコメントをいただきました。
ユーザー交流会終了後も1時間以上、同会場での個別の会話が続きました。さらに一部の方はその後場所を変えて深夜まで続きをされていたとの噂も・・・(^^)。
清水様、石毛様、参加者の皆様、大変有意義なディスカッションを実現いただきありがとうございました。


PM・SE・マーケティングなど多彩なバックグラウンドを持つ「データ連携」のプロフェッショナルが、専門領域を超えたチームワークで「データ活用」や「業務の自動化・効率化」をテーマにノウハウやWarp活用法などのお役立ち情報を発信していきます。

![MDMコラム[入門編]第1回:マスターデータ管理(MDM)とは?メリットや進め方、導入事例をご紹介!](https://www.asteria.com/jp/wp-content/uploads/2013/01/warpblog_88671186_title01.png)
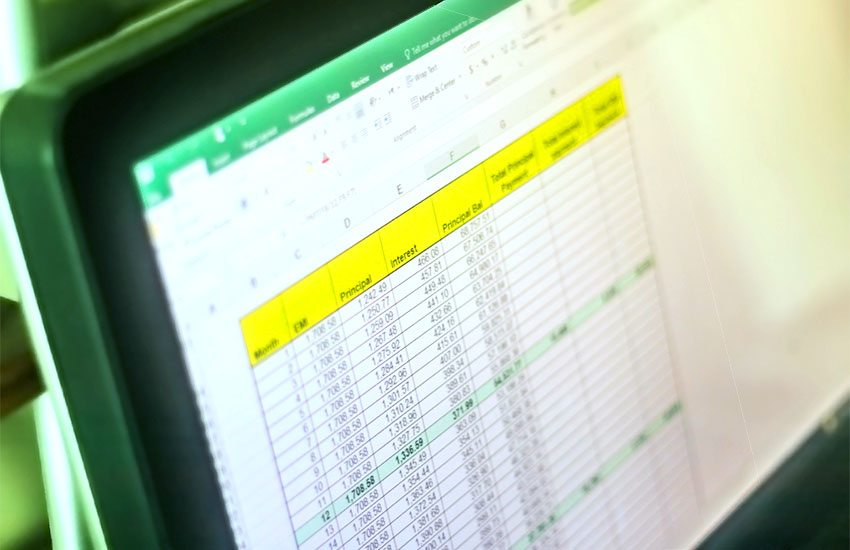


Related Posts

ASTERIA Warp製品の技術情報やTips、また情報交換の場として「ADNフォーラム」をご用意しています。

アステリア製品デベロッパー同士をつなげ、技術情報の共有やちょっとしたの疑問解決の場とすることを目的としたコミュニティです。