
クラウド移行に関して解説をする前に、まずはクラウド移行そのものがどういったものか、という点について解説をしていきましょう。
クラウド移行とは、自社のデータ資産をパプリック、あるいはプライベートクラウド上に保存することや社内業務システムをクラウド上の作業に移行することを指します。クラウドとは、ユーザーがインフラ(ソフトウェアやハードウェアなど)を有していなくても、インターネットを介して利用することができる仕組みを指しており、クラウドシステムを利用してサービスを提供しているのがクラウドサービスです。代表的なクラウドサービスと言えば、GoogleのGmailなどのWebメールが当てはまります。
クラウドには類似する概念として「オンプレミス」が存在します。オンプレミスとは自社でソフトウェア・ハードウェアなどを管理し、システムを自社で構築する運用方法です。
オンプレミスとクラウドの違いは下記の表を参照してください。
| 特徴 | オンプレミス | クラウド |
|---|---|---|
| 運用方法 | 自社運用 | 他社運用 (外部のクラウドサーバーを利用) |
| 導入コスト | 高い | 低い |
| 運用コスト | 主に設備のメンテナンス費用、ライセンス更新費用、保守に伴う人件費など | 従量課金制 (大規模システムや長期間の運用では高額になることも) |
| 構築期間 | 非常に長い | 短い |
| セキュリティ | 自社で直接管理できるため柔軟性が高い | 大手のクラウド事業者であれば高度なセキュリティ対策を実施していることが多い |
| 運用の自由度 | 高い | 低い (決まった機能しか使えない) |
| トラブル対応 | 自社対応自己責任 | サービス上の問題であれば対応して貰える |
| リモートワーク適正 | 低い (リモートワーク前提で構築した場合は除く) |
高い (インターネット上であれば場所を問わずに利用できるため) |
続いてクラウド移行を行う際のメリットについて解説していきましょう。クラウド移行を行うメリットは以下の6つです。それぞれ解説していきます。
クラウドの最大のメリットは、「元になる機材を用意しなくても良い」ということです。これはどの業界においても共通することで、単純に一から機材を買い揃える必要が無いだけでなく、型落ち・スペック不足のハードウェアでも擬似的に高性能なハードウェアで機能を扱うことができます。そのため、機材が充実していない中小企業でも、データだけでなく、システムを低コストで導入できます。
機材は用意すればそれで終わりというわけではなく、メンテナンスなど維持管理が必要です。オンプレミスでの構築では、自社でサーバーを運用するためサーバー機器が必要となります。それらのメンテナンスにはコストがかかるほか、障害対応など開発メンバーの人件費などもかかります。
クラウドでももちろん運用工数はかかりますが、サーバーのメンテナンス・障害などの対応よりも対応工数は減るでしょう。
クラウドサービスは、インターネットを利用できる環境であればサービスを利用できるというのが特徴の1つです。そのため、時間や場所を問わずに利用できるのがメリットと言えるでしょう。
勿論メンテナンスなど、どうしても利用できないという時間は存在しますが、それでも自前で機材を揃えて24時間利用できるようにすると維持コストが非常に高くなるため、オンプレミスでは場所や時間を限定することもあります。そういった点で見ても、いつでもどこでも使えるというのはメリットとして大きいと言えるでしょう。
オンプレミスでは、容量を増やそうと思うと当然機材を購入して増設しなければなりません。HDDやSSDのような単純な容量の拡張であれば容易ですが、サーバーなどを増設しようとすると、昨今の半導体不足による供給量の低下も合わさって調達に苦労します。
しかし、クラウドサービスであれば最初からある程度容量の拡張に対応しているため、必要になった際に容易に容量を拡張できます。
クラウドサービスは利用開始までの時間も短いのが特徴です。基本的な準備は既に終わっていて、用意されているものを使うだけなので、導入の手続きさえ終わればすぐに利用できます。クラウド移行も自社での移動準備が整えば、導入後すぐに移行を始められます。
ただし、出来ないことや制限がかかっている機能などもあるため、利用する際にはそういった注意事項に気をつけましょう。
オンプレミスでの構築では、サーバーなどの機器が必要となる場合があります。それらの機器の老朽化によって、トラブルやメンテナンス・買い替えが必要となるのもオンプレミスにおけるデメリットです。
クラウドは基本的に最新の環境を利用できるので、サーバーなどハード面での老朽化による買い替えは発生しません。
メリットの次はクラウド移行を行う際のデメリットと注意点について解説していきましょう。クラウドは移行オンプレミス環境と比較して従来のアナログな情報保存に比べて利点が豊富ですが、同時に勝手が全く異なるため特有のデメリットと注意点が存在します。
クラウド移行のデメリットは下記の通りになります
それぞれ解説していきましょう。
オンプレミスの場合は、自社の環境を前提として構築できるため、自社システム間で互換性を持たせることができます。しかし他社のクラウドサービスは当然他社が用意した環境であるため、自社のシステムとの連携が難しい場合があります。独自仕様が多いシステムを自社で採用している場合は注意しましょう。
カスタマイズできるのはサービスで利用できる範囲内のため、どうしてもカスタマイズには限界があります。特に上記で解説したように、自社システムとの連携ができるように調整するというのも難しく、どうしても調整したいというのであれば自社システム側を改良しなければなりません。
ネット上のやり取りには欠かせないもの、それがセキュリティ対策です。物理的な書類というものは保管しておけば、それを盗み出されるリスクは限りなく低いと言えるでしょう。なぜなら実際にその場に足を運び、保管している場所から取り出し持ち去るというような行動を必要とするためで、インターネット上ではその場から動くことなく、ハッキングによって遠隔でデータを盗み出すことが可能です。自社でクラウドサービスのセキュリティ対策はなかなか難しいため、セキュリティが保証できるサービスを選択することが重要です。
デメリットを解説した次はクラウド移行に対するリスクとその対策について解説を行います。
クラウド移行は、その名の通り既存の手段から完全に別の手段へと移行することです。その過程で発生するトラブルや、全く異なるものに対する忌避感というものはどうしても発生し得るものです。しかし、それらトラブルに対策を講じておくことで、クラウド移行を滞りなく進めることができるでしょう。
クラウド移行では、それまで自社サーバー(オンプレミス)で管理していたデータをインターネット上に保存することになります。そこで発生するリスクの1つがデータの損失です。もちろんオンプレミスでもこれはシステム的なエラーによって失われる場合も稀にありますが、データ損失が発生する最大の原因はヒューマンエラー、つまり人の手によるミスです。
しかし人間はどれだけ気をつけたとしてもミスをしてしまうもので、完全にミスをしないようにするというのは不可能であると言えます。そのため、データ損失を防止するのであれば、データのバックアップを事前にとっておくというのが最も確実と言えるでしょう。
アナログからデジタルへ、大きな変化には抵抗を覚える方は少なからずいます。それは単純な「理解できないことに対する忌避」であったり、「保守的思考」であったり、理由はさまざまでしょう。しかし、企業のデジタル化が推進されている現代において、既存のシステムを維持しようとする保守的思考は企業の息の根を止めてしまうことになるかもしれない、まさに命取りな思考と言えます。
そのため、変革に対して抵抗感のある人をいかに納得させられるかが重要です。そのためにはただ有用性や機能を訴えかけるだけでなく、具体的な使い方や操作方法などを説明して理解してもらうことが有効です。
単一のクラウド環境に依存すると、障害発生時の影響やコスト上昇など、さまざまなリスクが生じます。そこで注目されているのが、複数のクラウドを組み合わせて活用する「マルチクラウド連携」です。
ここでは、単一のクラウド運用における課題とマルチクラウドの利点、さらに運用面で注意すべきポイントについて解説します。
特定のクラウド事業者に依存して運用している場合、いくつかの課題が生じます。まず挙げられるのは、ベンダーロックインです。特定ベンダーのサービス仕様や料金体系に左右されやすく、価格改定や機能変更の影響を受けやすい傾向があります。その結果、他のクラウドへ移行しようとすると多くのコストや工数が発生し、柔軟な運用が難しくなります。
また、障害やシステム停止が発生した際には、単一クラウドでは代替手段を確保できず、業務全体が停止する可能性があります。事業継続計画(BCP)の観点からも、リスク分散が不十分な状態です。
さらに、クラウドごとに得意分野や提供機能が異なるため、単一利用では最適なサービスを選択しづらく、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進にも制約が生じます。
単一クラウドのリスクを回避する方法として注目されているのがマルチクラウド運用です。複数のクラウドサービスを組み合わせることで特定ベンダーへの依存を抑えられ、契約条件や価格に対する交渉力を高めることができます。新しいサービスや料金プランが登場しても、柔軟に乗り換えや追加導入が可能です。
また、障害が発生した際にも他のクラウドで業務を継続できるため、事業継続性(BCP)の強化につながります。さらに、クラウドごとに得意分野が異なるため、用途に応じて最適なサービスを選択でき、AI活用やデータ分析などのDX推進にも有効です。
マルチクラウドは、コスト・リスク・技術のバランスを取りながらシステムを進化させる手段といえるでしょう。
マルチクラウドはシステムの柔軟性を高める一方で、課題も存在します。まず、複数のクラウドサービスを利用することで、接続方式やデータフォーマットが異なり、統一的な接続管理が難しくなります。たとえ接続できても、データ変換や処理タイミングの制御が複雑化し、業務に活用できる連携ロジックの構築が容易ではありません。
また、スクリプトや担当者のノウハウに依存した運用では、ドキュメント整備が追いつかず、ブラックボックス化を招く恐れがあります。さらに、クラウドサービスは頻繁にアップデートされるため、仕様変更に迅速に対応できなければ、システム間の連携が停止したり、データの整合性が損なわれたりするリスクもあります。
マルチクラウド連携の課題を解決する方法については、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
ここからは実際にオンプレミスからクラウドに移行した事例を紹介します。オンプレミスからクラウドに移行する際にはデータの損失というミスを防ぎながら効率的に行うことが鍵となります。データ連携ツールなどを活用しながらそれぞれのデータをミスなく移行しましょう。
代表的なデータ連携ツールとしては、ノーコードで開発が可能な「ASTERIA Warp」があります。ASTERIA Warpは100種類以上の接続先が用意されているので、スムーズな移行が可能な連携ツールとして、様々な業種や用途で10,000社以上の企業に導入されています。
今回はその中からいくつか事例をご紹介します。
ピアサービス株式会社では、オンプレミス環境でのサーバーメンテナンスを行う管理者不足やコストなどが問題となっていました。中でもサーバー内にあるファイル数は60万を超えており、手作業でBoxに移行させることは気が遠くなる作業です。
そこでASTERIA Warpを導入し、部署単位で並列に移行を行うことで約1ヵ月でのファイル移行を実現させました。
また、ASTERIA WarpにはBoxアダプターやテンプレートがあるため、基本処理を自分たちで汲む必要がなく、開発コストを大幅削減にもつながりました。
株式会社ゴルフダイジェスト・オンラインでは、社内全てのデータを管理するために300台に及ぶオンプレミスサーバーを保有していました。これによって稼働状況の監視やトラブル対応などの業務圧迫が起きていたほか、お客様の履歴などを管理するSQL上の顧客DBの処理能力が限界となっており転送作業に大幅な時間がかかっていました。
この状況を改善するためにASTERIA Warpを導入し、全サーバーのデータをパブリッククラウドへ移行しました。このデータ移行により、AWS上で全ての連携システムの稼働を始めることが出来たため、管理・トラブル対応の工数の削減はもちろんAmazon Auroraを活用しながら最新の顧客行動に基づくマーケティング活動が可能になりました。
以上、クラウド移行について解説していきました。クラウドサービスにはさまざまな利点が存在し、同時にクラウド特有の欠点も存在します。しかし、オンプレミスとして自社で全てこなすというのは中小企業には厳しいのもまた事実です。欠点やリスクを把握したうえで、それを考慮した運用や対策を行い、クラウドを活用することで業務をより効率化できるでしょう。
関連資料はこちらから。

PM・SE・マーケティングなど多彩なバックグラウンドを持つ「データ連携」のプロフェッショナルが、専門領域を超えたチームワークで「データ活用」や「業務の自動化・効率化」をテーマにノウハウやWarp活用法などのお役立ち情報を発信していきます。
![MDMコラム[入門編]第1回:マスターデータ管理(MDM)とは?メリットや進め方、導入事例をご紹介!](https://www.asteria.com/jp/wp-content/uploads/2013/01/warpblog_88671186_title01.png)


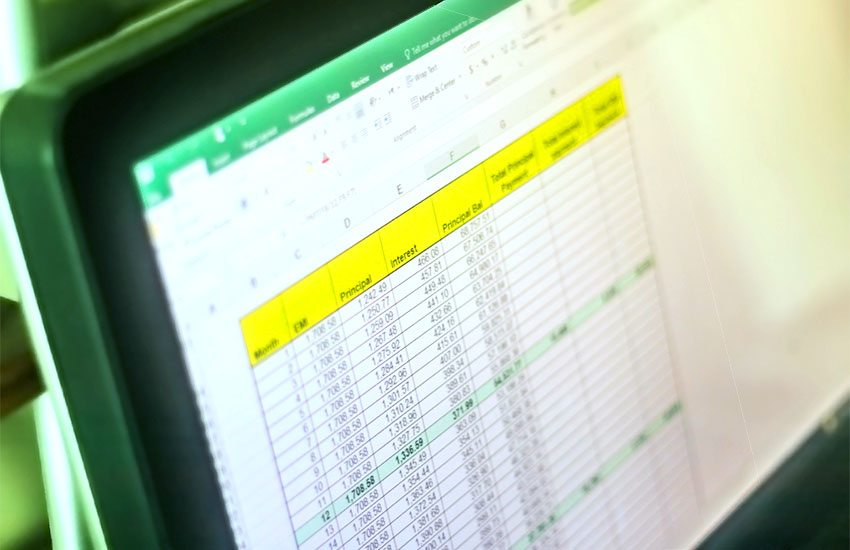


ASTERIA Warp製品の技術情報やTips、また情報交換の場として「ADNフォーラム」をご用意しています。

アステリア製品デベロッパー同士をつなげ、技術情報の共有やちょっとしたの疑問解決の場とすることを目的としたコミュニティです。