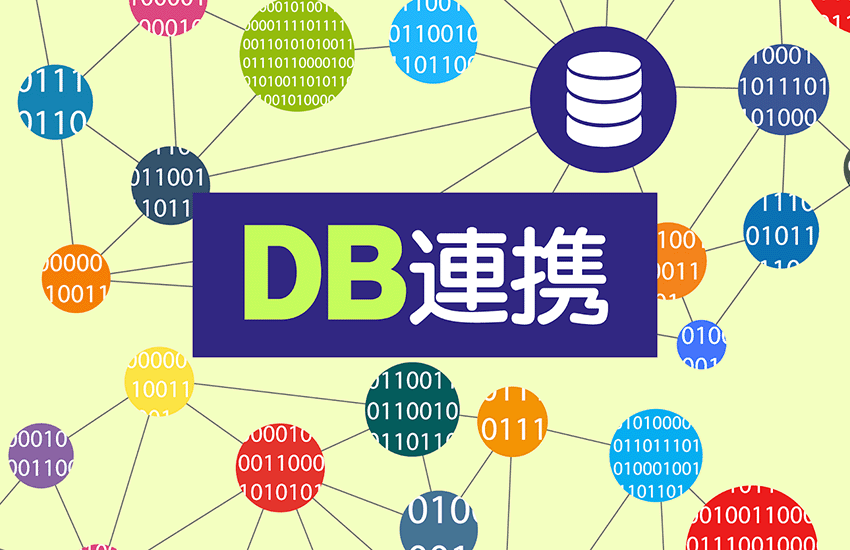
目次
「DB連携(データベース連携)」とは、人事・給与データや販売データ、顧客データなどの用途に沿って格納・管理された異なるシステムのデータベースにあるデータを紐付けする事です。それぞれのデータベースで管理されているデータを同期したり、組み合わせて利用するのに「DB連携」が必要になります。
また、似たようなものとして「データ連携」という用語があります。データベース連携は異なるシステムのデータを結び付けるのに対して、データ連携とは、システムやクラウドサービス、ファイルなど異なる保管場所にあるデータを組み合わせる事を指します。
データ連携の詳細はこちらを参照ください。
企業や官公庁といった組織内では、様々なシステムが運用されていますが、例えば製造業であれば生産管理や在庫管理、販売管理といったシステムが稼働しているでしょう。生産や販売にかかわる業務システムでも、そこに接続されるデータベースには、基本的にはそれぞれのシステムで支援している業務を行うのに必要なデータが保持されています。
次に小売業を例にとってみましょう。店舗やECサイト、あるいはコールセンターなど、顧客接点ごとにシステムが利用されていますが、例えばコールセンターのシステムでは、問い合わせをしてきた顧客が、過去に店舗やECサイトで、いつ、何を買ったかという情報を踏まえた応対がサービス品質向上のうえでは不可欠です。つまりこのケースであれば、少なくともコールセンターシステムのデータベースが、店舗やECサイトのシステムのデータベースと連携されている必要があります。一例になりますが、DB連携によって目指される目的はさまざまです。
それぞれのシステムが保有するデータの付加価値を高めるなど、他のシステムのデータベースで管理されている情報をあわせて活用することで、さらなる業務の効率化やサービス品質を向上させる為にDB連携が重要な役割を果たします。
ここでも小売業を例に詳しく説明すると、店舗システムのデータベースには、店舗顧客や顧客の購買にかかわる情報が管理されており、ECサイトのシステムのデーベースについても同様、ECサイトでの顧客やその購買履歴にかかわる情報が保持されています。
またコールセンターのシステムでは、顧客ごとの問い合わせ履歴などの情報は分かりますが、応対品質をより良いものとするために必要な、店舗やECサイトでの顧客の購買履歴を知ることはできません。
そこで、コールセンターシステムのデータベースを、店舗やECサイトのシステムのデータベースと連携し、双方のシステムが持つ購買履歴のデータを取り込んで、あわせて参照できるようにすることで、それぞれのシステムが保有するデータの付加価値を高めるなど、DB連携が重要な役割を果たします。
では、DB連携によってどのようなメリットが生まれるのでしょうか。それについては、さまざまなことが考えられますが、とくに大きなメリットとなる3点について説明していきましょう。
例えば、異なるシステムで同様のデータを扱っているような場合、片方のシステムにデータを入力するだけで、他のシステムのデータベースにも同期されれば、業務ごとに同じ入力作業を行わずにすみます。
人手による入力データの同期にかぎらず、あるシステムで発生したトランザクション等によってデータベース上のデータが更新された際にも、連携先システムのデータベースへもリアルタイムで同期が行われることで、最新のデータを連携先システム全体で共有が可能です。
冒頭で述べた通り、異なる業務目的で分散稼働しているシステムのデータベースを、関連する業務間で統合、共有するというアプローチも考えられます。ただし、そうすると統合化されたデータベースに対するアクセスが過多の状態になってレスポンスの低下が懸念されるほか、万一データベースに障害が発生すれば、そこにアクセスしているシステムがサービスを提供している広範な業務に影響が及んでしまうという問題もあります。つまり、各々のシステムでデータベースを分散稼働させることで、DB連携によって必要なデータをやりとりすることはシステム的なリスク回避にもつながります。
DB連携の実施にあたっては、いくつかの注意点が存在します。まずあげられるのが、セキュリティにかかわる問題です。データベースに格納されている情報は、例えば顧客や、自社の提供する製品・サービスにかかわる情報など、企業にとって重要なものであるケースも多いはずです。これに対し、DB連携のためにネットワークを介した通信を行わなければならないというケースも少なくありません。そうした際には、情報漏えいのリスクが懸念され、通信の暗号化などの対策を実施することが不可欠です。
あわせて、データの送受信についての性能や信頼性をどう担保するかという点も重要なポイントです。DB連携のアプローチを選択する際にも、そうしたセキュリティや性能、信頼性といった点について十分な考慮を行う必要があるでしょう。
DB連携には、大きく3つの方法があります。SOAPベースのWebサービスやRESTによるデータの受け渡しなどもありますが、データベースそのものをつなぐ、いわば本来の意味でのDB連携といえるアプローチには、以下のようなものがあります。
DBMS(DataBase Management System)とは、データベースを管理したり、アプリケーションなどがデータベースにアクセスして、参照・操作を行うためのソフトウェアを指します。ここまで単に「データベース」と記してきたところは、すべてDBMSとほぼ同義です。そうしたDBMSとしては、例えばベンダー製品であるOracle DatabaseやSQL Server、Db2のほか、オープンソースソフトウェア(OSS)のMySQLやPostgreSQLなども広く利用されていますが、それらの主要DBMSでは、リモートのデータベースサーバーにあるテーブルをあたかもローカルのデータベースサーバー上にあるかのように見せる「データベースリンク」と呼ばれる機能が提供されています。これを利用することで、分散稼働するデータベース間での連携を実現することができます。ただし、連携元、連携先が同一のDBMSに限った連携となる点に注意する必要があります。
EAI(Enterprise Application Integration)は、バッチおよびリアルタイムによるシステム間のデータ連携を行うツールです。オンプレミス環境やクラウドで企業が運用している自社システムを含む様々なシステムをつないだデータ連携が実現できます。データベースに関しては、プログラムがデータベースにアクセスするためのAPIであるJDBCやODBCによる連携をサポートしています。例えば、トランザクション処理によって、データベースレコードが更新される都度、リアルタイムな連携を行うといった用途に適しています。
「EAI」について詳細はこちらを参照ください。
ETL(Extract Transform Load)は、その名が示す通り、データを抽出(Extract)、変換(Transform)、出力(Load)するための仕組みです。さまざまなデータソースからのデータをバッチ処理で加工して、データ分析用のデータベースであるデータウェアハウス(DWH)に格納するという用途で活用されてきたツールですが、もともとDWH構築用途だけでなく、より広範な領域でのデータ連携に利用できるものであり、最近ではリアルタイムな連携を実現するものも登場してきています。適用用途としては、特にバッチ処理などで大量のデータを連携するというシーンで強みを発揮します。
「ETL」について詳細はこちらを参照ください。
代表的なEAI/ETLツールとしては、16年連続国内シェアNo.1を獲得しているノーコードのデータ連携ツール「ASTERIA Warp」がよく知られています。
最後にDB連携の事例を2つご紹介します。いずれもEAI/ETLツールである「ASTERIA Warp」で実現した事例になります。
リコージャパン株式会社は、オフィス向けの複写機/複合機を中心とした製品の開発・製造・販売で知られます。従来同社では、社内各所で運用されているNotes/Dominoデータベースにおいて、ハードウェアやシステムの保守を行う「ITサービス」にかかわる顧客の契約更新情報を管理していましたが、情報が一元化されていないため、営業担当者への更新案内がバラバラに通知され、ともすれば顧客への案内漏れといったリスクを抱えていました。これに対し、ASTERIA Warpを導入して当月の契約更新対象となる顧客の情報を抽出し、営業担当者にメール配信を行うシステムのデータベースへとデータを連携する仕組みを実現。これにより、顧客の契約更新をとりこぼしなく取り付けていける体制を整えることができました。
事例詳細はこちら
東建コーポレーション株式会社は、土地活用の提案からアパート・賃貸マンションの施工・管理、入居仲介など、土地・賃貸関連で幅広い事業を手掛けている総合建設業です。同社では、業務上とりわけ重要な基幹システム(IBM Db2)と業務支援システム(Oracle)を、これまで相互連携ツール「Oracle Transparent Gateway(OTG)」を利用していましたが、同ツールが保守切れとなることから、新たにASTERIA Warpを導入する運びとなりました。導入の結果、ランニングコストが大幅に低減。内製している連携処理の開発にも、ノーコードによる高度な生産性がもたらされているほか、データ連携基盤の高い安定性も実現することができました。
事例詳細はこちら
ここまでの内容から、DB連携がもたらす、例えばデータ入力にかかわる工数削減やデータ鮮度の担保などいくつかのメリットを紹介してきました。そして、なによりも重要なのは、さまざまな業務が互いに融合し、ビジネスにおけるシナジーを発揮していくことが求められる時代にあって、データベースに格納されたそれぞれに価値あるデータがつながりあうことで、そこにさらに新たな価値が創出されていくということです。
それに向けては、ASTERIA Warpのように多彩なデータソースとの連携をスピーディに実現できる、実績豊富なツールを選択することが望ましいといえるでしょう。

PM・SE・マーケティングなど多彩なバックグラウンドを持つ「データ連携」のプロフェッショナルが、専門領域を超えたチームワークで「データ活用」や「業務の自動化・効率化」をテーマにノウハウやWarp活用法などのお役立ち情報を発信していきます。

![MDMコラム[入門編]第1回:マスターデータ管理(MDM)とは?メリットや進め方、導入事例をご紹介!](https://www.asteria.com/jp/wp-content/uploads/2013/01/warpblog_88671186_title01.png)
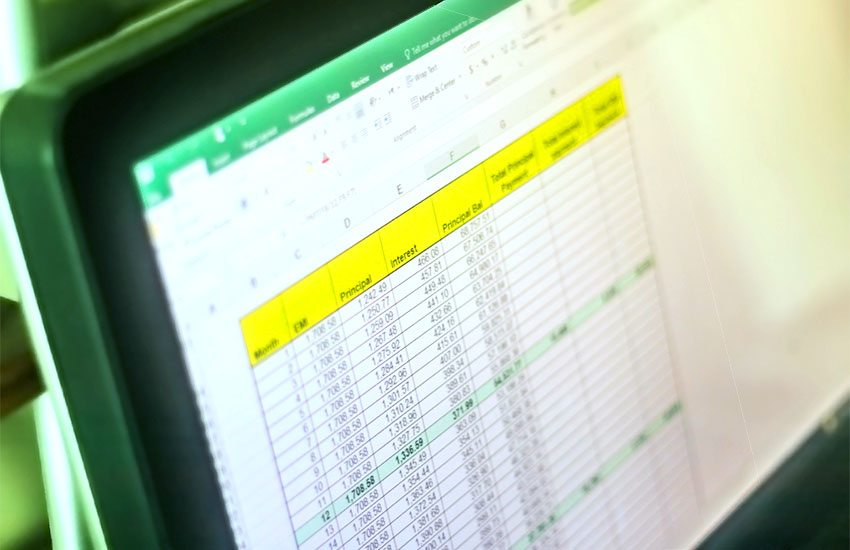



ASTERIA Warp製品の技術情報やTips、また情報交換の場として「ADNフォーラム」をご用意しています。

アステリア製品デベロッパー同士をつなげ、技術情報の共有やちょっとしたの疑問解決の場とすることを目的としたコミュニティです。