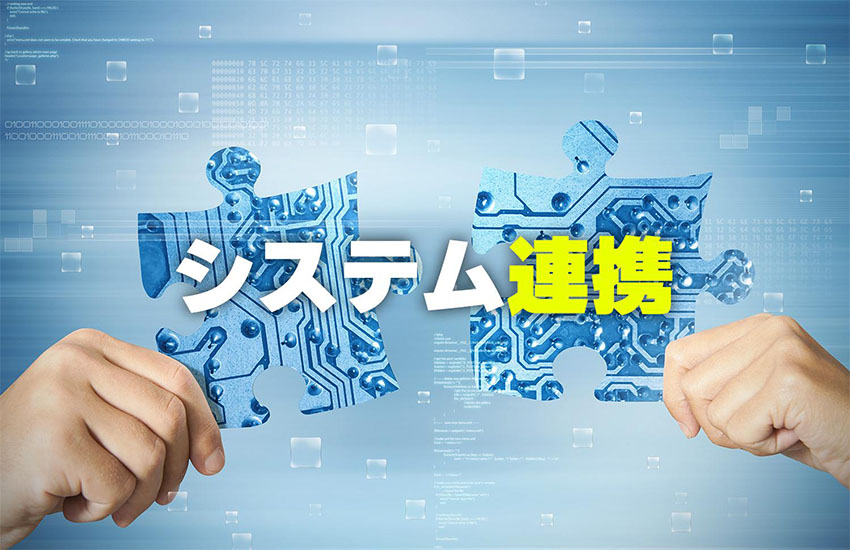
様々なデータを取り扱う昨今のビジネスにおいて、個別に管理している業務システムやアプリケーションを連携させることで、業務の効率化やデータ活用を推進したいと考える企業担当者の方も多いのではないでしょうか。しかし、近年では様々なシステム連携の方法があるため、自社の業務内容や課題に合わせた適切なシステム連携方法の選定が重要になります。本記事では、システム連携が必要とされる理由、メリットやシステム連携を行う際の課題について解説するとともに、システム連携による業務効率化に成功した事例をご紹介します。
目次
システム連携とは、複数の異なるシステムやアプリケーションを連携して、データを共有できる環境を構築することをいいます。多くの企業では、複数の社内システムに大量のデータを保有していますが、システムごとに独立した状態では業務に活用することは困難です。これらのデータを連携することで、より効果的な業務効率化や、データの活用をすることが可能となります。
業務効率が低下する原因の一つに、システムやデータの「サイロ化」が挙げられます。「サイロ化」とは、組織内のデータやシステムが独立して運用され、部門間での情報共有が難しい状態を指します。
サイロ化されたシステムやデータは、業務効率やデータ信頼性の低下、顧客対応の遅れ、データ管理コストの増加など多くのデメリットを引き起こします。
社内に多くのデータが蓄積されていても、サイロ化が起こると効果的なデータ活用が困難になります。これらを改善するためにシステム連携が重要となります。システム連携を実施することで、部門間の情報共有が容易になり、業務効率の改善や顧客満足度の向上が期待できます。
システム連携を行うことで、次のようなメリットが得られます。
以下では、システム連携を行うメリットについて詳しく解説します。
異なるシステム同士のデータ共有を手作業で行う場合、システムからデータの収集や変換、加工作業を行う必要があるだけでなく、各工程において入力漏れや打ち間違いがないか、といったチェックをする手間も発生します。システムを必要に応じて連携させることで、ファイル形式の変換作業やチェック作業の負担が減り、データの迅速な共有が可能になり、業務プロセスが効率化されます。
また、複数システムへの多重入力など手動でのデータ入力が不要になるため、入力ミスといったヒューマンエラーのリスクも回避できます。これにより、情報の正確性も期待できます。
企業には、さまざまな部門やチームが存在し、それぞれが独自のシステムやデータベースをもっています。システム連携によりこれらを一元化することで、組織全体で信頼性の高い最新のデータを利用することができるようになります。
例えば営業部門が商品在庫や納期情報をリアルタイムで確認できれば、顧客への対応が迅速かつ適切に行えます。
システム連携を実施しデータを統合することで、全容を可視化しデータを効果的に活用することができるようになります。
システム連携をすることで、データ管理のコスト削減に繋がります。特に、重複するデータ管理によるコストを削減できるのは大きなメリットです。
複数のシステムが独立して運用されている場合、各システムに同じデータを入力する多重入力や、それぞれのシステムでデータを更新する必要もあります。このような重複した管理作業は、無駄な時間と労力を消費するだけでなく、データの整合性を損なう原因にもなります。
システム連携により異なるシステム間でデータを共有することで、手作業でのデータ入力や更新など、管理作業に要する様々なコストを削減できます。
サイロ化しているシステムを連携することで、異なる部門やシステム間でのデータ共有がスムーズになり、部門内でしか活用されていなかったデータを全社的に一元管理することで、新たな価値やビジネスチャンスを生み出せるようになるでしょう。
システム連携をすることで多くのメリットが得られますが、実施には課題・注意点があります。
システム連携によって扱うシステムが増えると、開発や運用のコストが増加することがあります。そのため、システムが増えた場合の対応工数も考慮する必要があります。
また、システム連携ツールの選定によっては、業務効率が低下する恐れもあります。同時にシステム連携が属人化してしまうことでシステムの改修などが難しくなってしまうこともあります。もちろん手組みの開発でシステム連携を行う場合にも同様のことが言えます。
システム連携には「手組」「EAI・ETLツールを使用した連携」といった方法があります。以下では、これらのシステム連携について詳しく解説します。
システム連携の方法の一つとして「手組」が挙げられます。「手組」は「スクラッチ開発」や「フルスクラッチ」とも呼ばれており、企業のニーズに合わせて、システムをゼロから独自開発し連携する方法です。
システムを手組で開発することで、独自の仕様や要件に対応するシステムを構築することが可能で、独自の自社システムとの連携もできるといったメリットがあります。
ただし、スクラッチ開発には高い技術力や専門知識が必要です。開発期間やコストが高くなる傾向や属人化する恐れもあるため、慎重に検討することが求められます。
システム連携ツールには、大きく分けてETL(Extract Transform Load)とEAI(Enterprise Application Integration)の2種類があります。
ETLは、異なるデータソースからデータを抽出(Extract)し、用途に合わせて変換(Transform)した後に、新しいデータベースやデータウェアハウスに格納(Load)します。データを集約することを目的としているため、大量のデータを定期的に連携するのに適していますが、EAIツールのようにリアルタイムに連携するのには向いていません。
ETLについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
EAIツールは、企業内の異なるアプリケーションやシステムを統合することを目的としており、データの連携を迅速に行うことが可能です。ただし、システム間のデータ処理をリアルタイムで行えますが、大量のデータを連携するのには向いていません。ETLとEAIの違いについては以下の記事で詳しく説明しています。
従来は、システム連携を行うためにプログラミングなどの専門的な知識を必要としていました。しかし、近年はノーコードのEAIツールやETLツールが主流となっています。
ノーコードツールを使う最大の利点は、専門的なプログラミングスキルがなくてもシステム連携が可能なことです。ノーコードツールであれば、直感的なドラッグ・アンド・ドロップ操作やビジュアルインターフェースによって、誰でも簡単にシステム連携を行えます。
専門的な技術を必要としないため、業務をよく知る現場スタッフが担当することもできますし、属人化のリスクをなくすことが出来るのも大きなメリットといえるでしょう。
ただし、ノーコードツールを選択する際は、自社の要求や目的に合ったツールを選択することが重要です。「連携したいシステムに対応しているか」「問題が起きた際にサポートをしてもらえるか」など、自社に適したノーコードツールを選ぶことが重要です。
専門的な技術や知識を必要とするシステム連携ですが、データ連携ツールの「ASTERIA Warp」を導入することで、直感的な操作で誰でも簡単にシステム連携を行うことができます。以下では、「ASTERIA Warp」を導入した企業によるシステム連携の事例についてご紹介します。
三機工業株式会社様は、建設設備や搬送設備など、様々なインフラ事業を展開しています。同社は、LCE事業の推進を実現するために、Googleマップを利用した施工物件検索システムを「Microsoft Dynamics 365」上に構築していましたが、既存のデータベースは物件名や住所の変更に対応できていませんでした。
そこで、Microsoft Dynamics CRMアダプターを使い、基幹システムとの連携を内製開発しました。さらに、ASTERIA Warpを使用した月次処理で約100万件のデータを検索し、約2,000件をMicrosoft Dynamics 365に反映しました。
本来、プログラムを自社開発すると膨大な開発工数がかかりますが、プログラミングスキルのない部員でも2ヶ月でデータ連携や処理設定を行うことができました。
三機工業株式会社様の導入事例について、詳しくは下記をご参照ください。
IMV株式会社様では、環境試験や計測、解析装置の製造・販売を行っています。これまで、販売や生産の管理をオンプレミスの基幹システムで行っていましたが、作業負荷が大きいなどの課題を感じるようになりました。
そこで、改善のために、Salesforceなどのクラウドサービスを導入しましたが、複数のシステムを運用していたために、データの整合性を取るチェック業務が増えてしまいました。
そこで「ASTERIA Warp Core」を導入して、基幹システム、Salesforce、kintoneのデータ連携の自動化を実現しました。Google WorkspaceやMicrosoft Accessとも連携し、自動化したことにより、工数の削減やヒューマンエラーの減少ができ、業務品質アップにつながりました。
IMV株式会社様の導入事例について、詳しくは下記をご参照ください。
東建コーポレーション株式会社様では、アパートや賃貸マンションの施工、入居仲介などの事業を展開しています。同社では基幹システムと業務支援システムを利用しており、営業日報や物件情報などについて、それぞれのシステムで登録・更新を行っていました。
データ連携にはOracle Transparent Gatewayを使用していましたが、保守が切れたタイミングに合わせて、低コストで安定性・信頼性の高い連携方法を検討した結果、初期費用ゼロ・月額6万円で導入可能な「ASTERIA Warp Core」を選択することとしました。
これにより、機能や開発工数は変わらず、ランニングコストを約7割削減することができました。東建コーポレーション株式会社様の導入事例について、詳しくは下記をご参照ください。
本記事では、システム連携の概要とその方法について解説しました。システム連携には、手組開発やツールを利用した連携など、さまざまな方法があります。
システム連携には専門的な知識が必要とされますが、ノーコードのデータ連携ツールを活用することで、プログラミングスキルがなくても簡単に実現することができます。
適切にシステムを連携することで、データ活用の拡大や業務効率化が期待できます。ぜひ、自社に最適な連携方法を選択し、スムーズにデータ連携を行いましょう。

PM・SE・マーケティングなど多彩なバックグラウンドを持つ「データ連携」のプロフェッショナルが、専門領域を超えたチームワークで「データ活用」や「業務の自動化・効率化」をテーマにノウハウやWarp活用法などのお役立ち情報を発信していきます。


![MDMコラム[入門編]第1回:マスターデータ管理(MDM)とは?メリットや進め方、導入事例をご紹介!](https://www.asteria.com/jp/wp-content/uploads/2013/01/warpblog_88671186_title01.png)
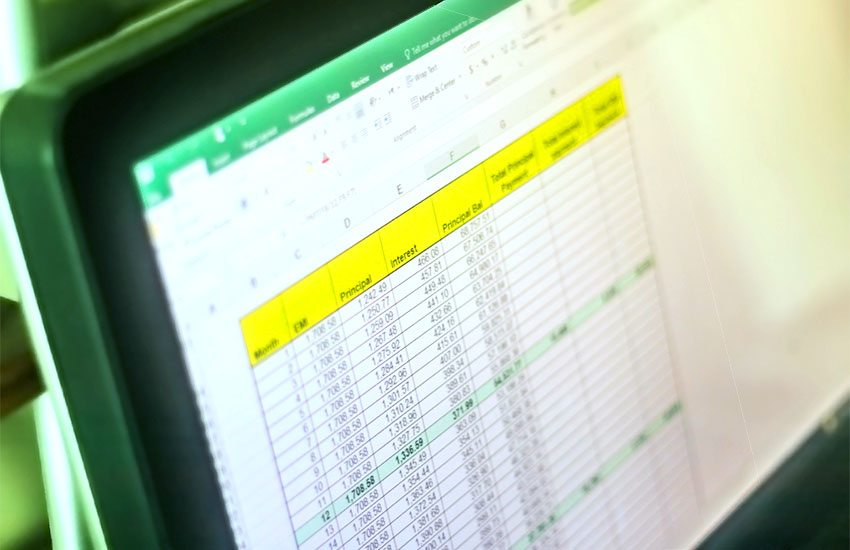


ASTERIA Warp製品の技術情報やTips、また情報交換の場として「ADNフォーラム」をご用意しています。

アステリア製品デベロッパー同士をつなげ、技術情報の共有やちょっとしたの疑問解決の場とすることを目的としたコミュニティです。