
企業が自社の保有するデータを分析・活用する際、社内に散在するさまざまなシステム間のデータを連携することが求められます。しかし、異なるフォーマットや文字コードなどで保管・管理されているデータを手作業で変換・連携処理することは課題も多く、容易ではありません。
そこで、スムーズなデータ連携を実現させるためには、「データ変換ツール」を活用して効率的に事前処理を進めることが一般的になってきました。
ただし、データ変換ツールには多くの種類があり、データ連携の目的や用途によって最適なツールを見極める必要があります。
本記事では、データ変換ツールの種類やメリットを分かりやすく解説し、選び方のポイントもご紹介しています。
目次
通常、企業内に点在しているデータ形式や構造が異なるデータを連携するためには、データの取得・変換・登録などの作業が必要です。しかしこれらを手作業で行う場合、膨大な時間と手間がかかるだけでなく、打ち間違いや変換ミスなどの人的ミスが発生する原因にもなります。そこで有効となるのが、データ変換ツールの活用です。
以下では、データ変換ツールを活用したデータ連携の方法として、代表的なツールであるETL、EAI、RPAについて、それぞれの特徴を詳しく解説します。
ETLとは、データを「抽出(Extract)」「変換(Transform)」「書き出し(Load)」というプロセスの略称で、大量のデータを集約・統合するのに適しているツールです。
例えば、営業・経理・マーケティングなど複数の部門が管理する売上データを一元化し、BIツール(ビジネスインテリジェンス)で分析する場合に活用されます。
異なるデータベースやフォーマットのデータを変換し、統一フォーマットに整えることでデータの品質を向上させ、分析やレポート作成がスムーズになります。そのため、データウェアハウス(DWH)と組み合わせて利用されるケースが多いのも特徴です。
EAI(Enterprise Application Integration)は、システム同士をリアルタイムで接続し、データのやり取りを行うツールです。
最大の特徴は「アダプター機能」を備えている点です。アダプターとは、異なる形式のシステムやデータベース、クラウドサービス同士を容易に接続する連携モジュールを指します。これにより各システムのインターフェースやプログラムを個別に開発することなく、異なるシステム間でのデータ連携を簡単に実現できます。
ETLとの違いは、データ処理のタイミングです。ETLがデータを一旦集約・変換し、あとから活用するのに対し、EAIは即座にやり取りする仕組みになっています。
そのため、在庫管理システムとECサイトの注文データを即時に連携し、在庫切れや販売ミスを防ぐといった用途に適しています。
RPA(Robotic Process Automation)は、業務プロセスを自動化するためのツールです。
データ入力やファイル操作などの定型業務をソフトウェアロボットが代行することで、作業時間の短縮や人的ミスの削減が可能になります。
データ変換の機能も備えていますが、あくまで業務自動化が主な目的のため、データ変換に特化しているわけではありません。
そのため、「変換元のデータが複数ある」「変換ルールが複雑」といった場合には、RPAだけでは対応しきれないケースもあります。
例えば、RPAを使ってExcelの請求書データを会計システムに自動入力することは可能ですが、複数のデータソースを統合するような高度な処理には向いていません。
よって、RPA単独ではなく、ETLやEAIと組み合わせて利用するのが一般的です。
データ変換ツールを導入することで、企業全体でのデータ連携がより効率的に進むようになります。ここでは、具体的にどのような利点があるのかを解説します。
システムに手作業でデータを入力すると、入力ミスや表記ゆれが発生しやすくなり、データの整合性が崩れるリスクがあります。
例えば、顧客名が「株式会社A」と「(株)A」と異なる表記で登録されると、同じ企業なのに別データとして扱われてしまうでしょう。
データ変換ツールはCSVやExcel、Oracle、SQL Serverなどさまざまな種類に対応しており、フォーマットが異なっていても自動的に統一します。データの一貫性が保たれ、正確な管理が可能になるだけでなく、業務の効率化やデータ分析の精度向上にもつながります。
複数のシステムから必要なデータを手作業で集めるのは、時間もコストもかかる非効率な作業です。
また、データの抽出や変換をエンジニアに依頼したり、外部のベンダーにカスタマイズを依頼したりすると、その都度高額な開発コストが発生してしまいます。
データ変換ツールを導入すれば、ワンクリックでデータの収集・変換を自動化できるため、作業時間を大幅に短縮し、費用的負担も軽減できます。
データ変換ツールには、フォーマット変換だけでなく、データの抽出・加工・統合・出力までを一括で処理できるものもあります。
営業・マーケティング・経理部門が別々のシステムを使っている場合でも、データ統合からリアルタイムでのデータ分析や予測が可能になり、意思決定の精度も向上します。
データ変換ツールの代表的な機能をまとめました。
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| マッピング機能 | 異なるデータソースやフォーマットのデータを紐づけし、統一フォーマットで管理できるようにする。 |
| 重複除去機能 | データの重複を検出し、一つのデータに統合することで、データの正確性を向上させる。 |
| 文字コード変換機能 | Shift_JIS、UTF-8、EBCDICなどの異なる文字コードを適切に変換し、システム間の互換性を確保する。 |
| 出力設定機能 | 条件に応じてデータの出力方法を変更し、必要な形式でデータを取り出せるようにする。 |
| エラー制御機能 | エラーが発生した際の処理方法を設定し、自動修正やログ記録などの対応を行う。 |
データ変換ツールには多くの種類があり、自社の業務環境や目的に合ったものを選ぶことが重要です。
導入後に「思ったように使えなかった」と後悔しないためにも、以下のポイントを踏まえてツールを選定しましょう。
データ変換ツールは、データベースやクラウドストレージ、業務アプリケーションと連携できるようになっています。
しかし、ツールによって対応範囲が異なるため、利用中のシステムと連携できるかを事前に確認しておきましょう。
また、将来システムを拡張する可能性も考慮し、接続可能なコネクタやアダプタの種類が豊富なツールを選ぶことをおすすめします。
直感的に操作できるインターフェースであれば、情報システム担当者だけでなく現場の担当者でも活用しやすくなり、業務の効率化がさらに進みます。
特にノーコード・ローコード対応のツールであれば、専門的な知識がなくても簡単にデータ変換の設定ができるため、初心者でも扱いやすいのがメリットです。
小規模なデータ連携であれば、無料版やシンプルな機能のツールでも十分に対応できる場合があります。しかし、大規模なデータを扱う場合は、複数のシステムを統合できるエンタープライズ向けのツールが必要になります。
また、長期的にデータ量が増加することを想定することも重要です。スケーラビリティ(拡張性)が高いツールを選ぶことで、買い替えや再構築のコストを抑えることができます。
データ変換ツールの料金体系には、「月額定額制」と「従量課金制」の2種類があります。
月額定額制は毎月一定額で利用するタイプです。データ量や処理回数が多い企業に適しており、コストの見通しが立てやすいのが特徴です。
一方で、従量課金制は使った分だけ料金が発生する仕組みのため、小規模なデータ変換を行う企業や使用頻度が低い場合にコストを抑えやすいメリットがあります。
海外製のツールは、マニュアルやサポート対応が英語のみの場合もあります。一方、国産ツールであれば、日本語のマニュアルやサポート窓口が充実していることが多く、安心して運用を進められます。
特に初めて導入する場合は、設定や運用時の不明点をすぐに解決できるかどうかを確認しておきましょう。
数あるデータ連携ツールの中でも、多くの企業に選ばれているのが「ASTERIA Warp(アステリア ワープ)」です。
選ばれる理由は、プログラミング不要で直感的に操作できる点、豊富な接続先、低コストで導入できる手軽さにあります。
ここでは、ASTERIA Warpの特長をご紹介します。
ASTERIA Warpはノーコード対応のため、プログラミングの知識がなくても簡単にデータ連携を構築できます。現場の担当者でも直感的に操作できるため、開発期間を大幅に短縮できるのが大きな強みです。
さらに、「Asteria Park」や「DevFes」などのユーザーコミュニティやイベントが充実しており、情報交換がしやすい環境が整っています。困ったときにも、実際の活用事例を参考にしながら解決策を見つけやすい点も魅力の一つです。
ASTERIA Warpは、100種類以上のシステムやクラウドサービスとの接続が可能です。例えば、以下のようなツールと連携できます。
既存のシステムやクラウドサービスと柔軟に連携できるため、業務の自動化・効率化・データ活用をスピーディーに実現します。
ASTERIA Warpには5種類のプランがあり、「ASTERIA Warp Core」なら月額30,000円〜で利用可能です。
初期費用はかからないため、導入時のコストを抑えながら手軽に始めることができます。
また、必要に応じてプランを変更できるため、スモールスタートから始めて、業務拡大に合わせた柔軟な運用が可能です。
データ変換ツールを活用することでデータ連携の効率化が進み、コスト削減や業務の自動化を実現できます。
導入にあたっては、接続先の豊富さ、操作のしやすさ、サポート体制などを確認し、自社のニーズに合ったツールを選ぶことが重要です。
中でも「ASTERIA Warp」は、ノーコードで直感的にデータ連携が可能で、100種類以上のシステムとスムーズに接続できる点が高く評価されています。
「まずはデータ連携について詳しく知りたい」という方は、以下の資料をダウンロードしてみてはいかがでしょうか。

PM・SE・マーケティングなど多彩なバックグラウンドを持つ「データ連携」のプロフェッショナルが、専門領域を超えたチームワークで「データ活用」や「業務の自動化・効率化」をテーマにノウハウやWarp活用法などのお役立ち情報を発信していきます。

![MDMコラム[入門編]第1回:マスターデータ管理(MDM)とは?メリットや進め方、導入事例をご紹介!](https://www.asteria.com/jp/wp-content/uploads/2013/01/warpblog_88671186_title01.png)

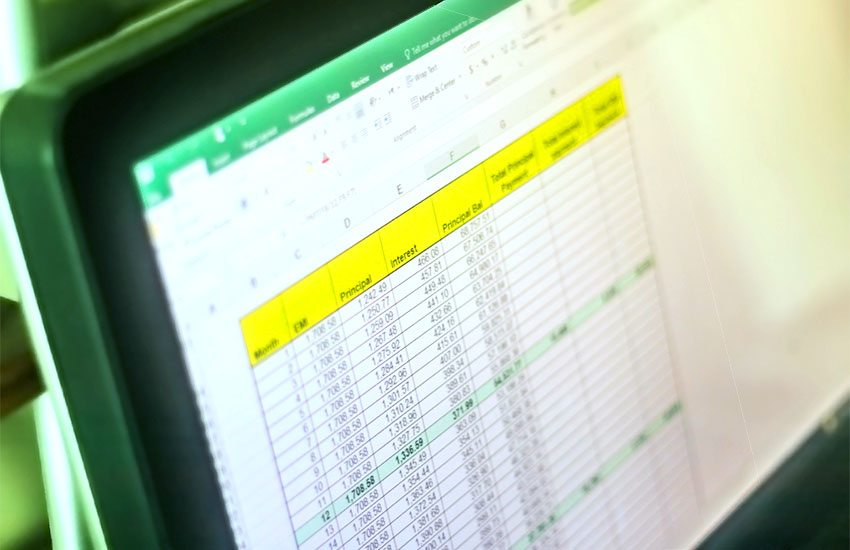

Related Posts

ASTERIA Warp製品の技術情報やTips、また情報交換の場として「ADNフォーラム」をご用意しています。

アステリア製品デベロッパー同士をつなげ、技術情報の共有やちょっとしたの疑問解決の場とすることを目的としたコミュニティです。