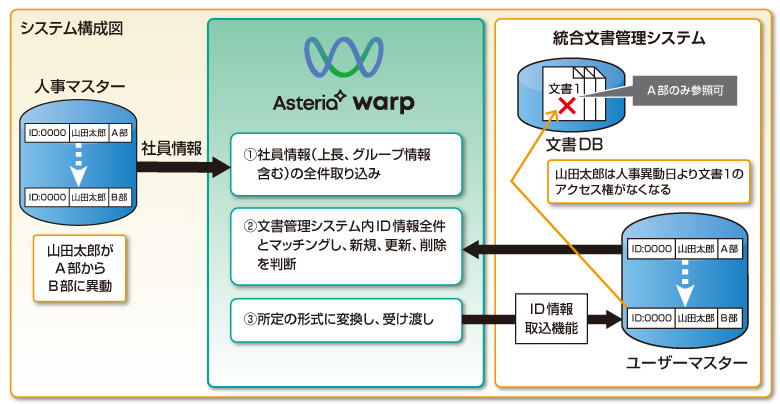ID連携の成果を受け
ASTERIA Warpの適用範囲を拡大
こうした成果と使い勝手の良さを評価し、同社はASTERIA WarpをID連携以外のケースにも適用し始めている。例えば統合文書管理システムのエラー発生を検知する仕組みにも、ASTERIA Warpを利用し始めた。統合文書管理システムに何らかの不具合またはスレッドのダウンが発生すると、サーバにエラーログファイルが生成される。このエラーログファイルの“数” を定期的にASTERIA Warpで読み取ってチェックし、しきい値を超えた場合に管理者に伝える仕組みとしたのだ。
スレッドのダウンは日常的に起こることから、そのことだけで問題が発生しているとは断定できず、常にエラーファイルの中身を目視で確認する必要があった。しかし通常よりも大量のエラーファイルが生成されているとなれば、何らかのクリティカルエラーが起きていると推定できるため、ASTERIA Warpにエラーファイル数を監視させることにしたという。「統合文書管理システムで発生するさまざまな不具合の中には、コンソールで監視しているだけでは死活状態が判定できないものもあり、ユーザーからクレームを受けて初めて障害に気づくというケースもありました。ASTERIA Warpを利用したこの仕組みによって、迅速な不具合の検出が可能となり、サービスレベルの向上に大きく貢献しています」(吉信氏)。システム監視ツールを導入すれば同様のことは実現できるが、手間とコストがかかる。ASTERIA Warpの簡単なフローでエラー監視が実現できたことは大きな成果だという。
また、統合文書管理システムに社内通知文書が登録されると、ASTERIA Warpが自動的にそのタイトルとリンクを社内ポータルサイトの特定位置に掲載するようにした。これにより社員が必ず参照しなければならない文書が、ポータルサイト上で一覧できるようになった。さらに総務担当者は、社員に通達したい統合文書管理システム上の文書リンクURLをExcelに記載するだけで、ASTERIA Warpが数分のうちに社内ポータルにリンクを掲載するという仕組みを利用している。このような仕組みもASTERIA Warpならば、わずか数日間で開発、サービスインできたという。「従来のようにその都度Webシステム担当者に掲載を依頼する手間もなくなり、『とても便利になった』と総務担当者からも好評です」(吉信氏)。
そして次に計画しているのが、統合文書管理システムの海外拠点への展開だ。「国内の既存ユーザー約6,000名に、新たに海外拠点のユーザー約1,000名が加わることになり、システムの大規模化に対応しなければなりません。ユーザーインタフェースの英語化、海外の個別事情に配慮した新たな情報統合など、検討すべき課題はまだ山積みです」(小林氏)。
田辺三菱製薬は今後、ASTERIA Warpを国内外のさまざまな課題解決に活用・展開することで、同社ICTのさらなる発展を図る。