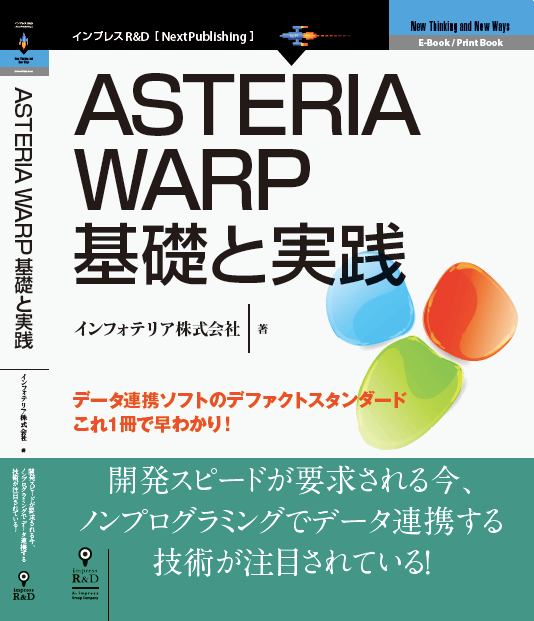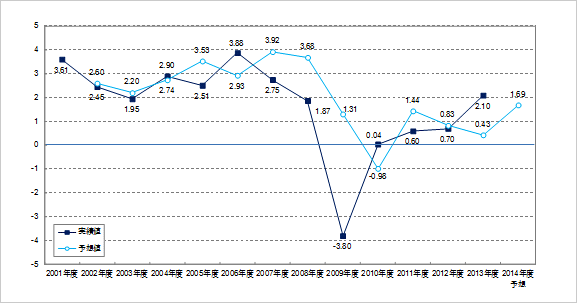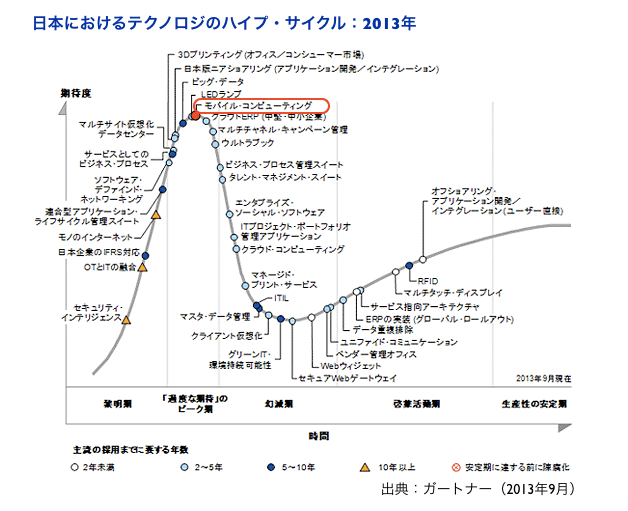※今回は、くまモンに敬意を表し、全編熊本弁でお届けします(笑)
導入社数4,000社ば超えたASTERIAの応援にくまモン登場ばい!!!!
写真のごて、くまモン × ASTERIAの初コラボによるミネラルウォーターの完成したばい!熊本が世界に誇る「阿蘇」の伏流水ば使こて、熊本の清涼飲料水メーカーさんにお願いして作ってもろたったい。よか感じでむぞらしゅ仕上がったて思うばってん、どぎゃんね!?
今回作ったとは、4,000社にちなんで、4,000本!ラベルの色は、もちろん緑色たい。阿蘇ん大地ば象徴する色でんあるけんね(笑)
原則的にゃ、くまモンは熊本に関係ある企業しか使われんとばってん、生粋の熊本県出身の上場企業創業社長ていうことで、熊本県庁の粋な計らいで特別に使わせてもろたったい。ほんなこてありがたか!
社長が熊本出身の割には、4,000社の中で熊本県の企業の割合は少のして社内で肩身の狭かばってん、去年は済生会熊本病院さんの事例も公開させてもろたし、こっばきっかけにぎゃんぎゃん増やしていかなんね思とっとこったい。熊本の企業の皆さん、あんまっせからしかこつば言わんで、なんさまASTERIAば入れてみてはいよ(笑)
くまモンは、「ゆるキャラNo.1」、ASTERIAは、「データ連携シェアNo.1」ていうこつで、同じNo.1同士ばってん、くまモンは、もう世界進出しとるけん、負けられんね!
くまモン、応援ありがとう!インフォテリアもがまだして世界さん行くけんね!!!!
【翻訳】
導入社数4,000社を超えたASTERIAの応援にくまモン登場です!!!!
写真のように、くまモン × ASTERIAの初コラボによるミネラルウォーターが完成しました!熊本が世界に誇る「阿蘇」の伏流水を使って、熊本の清涼飲料水メーカーさんにお願いして作っていただきました。いい感じでかわいく仕上がったと思いますが、どうですか!?
今回作ったのは、4,000社にちなんで、4,000本!ラベルの色は、もちろん緑色です。阿蘇の大地を象徴する色でもあるからです(笑)
原則的には、くまモンは熊本に関係ある企業しか使えないのですが、生粋の熊本県出身の上場企業創業社長ということで、熊本県庁の粋な計らいで特別に使わせていただきました。本当にありがたいです!
社長が熊本出身の割には、4,000社の中で熊本県の企業の割合は少なくて社内で肩身が狭いのですが、去年は済生会熊本病院さんの事例も公開させていただきましたし、これをきっかけにどんどん増やしていきたいと思っているところです。熊本の企業の皆さん、あまりうるさいことを言わず、とにかくASTERIAを入れてみてください(笑)
くまモンは、「ゆるキャラNo.1」、ASTERIAは、「データ連携シェアNo.1」ということで、同じNo.1同士ですが、くまモンは、もう世界進出しているので、負けられません!
くまモン、応援ありがとう!インフォテリアも頑張って世界に行くからね!!!!